▶オフィス・会議室・応接室のテーブル一覧はこちら
▶オフィス・会議室・応接室のチェア一覧はこちら
▶業務用 ブース/パーテーションの一覧はこちら
オフィス移転を検討する際、初期費用や工事期間に悩む企業担当者は多くいます。居抜きオフィスは、前テナントの内装や設備をそのまま引き継ぐため、従来の移転と比べて大幅なコスト削減と期間短縮を実現できます。さらに環境配慮やデザイン性の高さから、スタートアップから大企業まで幅広く注目されている新しいオフィス形態です。
居抜きオフィスの定義と基本構造
前テナントが残した内装や設備を活用する居抜きオフィスは、従来のスケルトン物件とは異なる契約形態と物理的構造を持ちます。オフィス移転における初期投資を抑えながら、短期間で業務を開始できる仕組みを理解するには、基本的な定義と構造要素を把握する必要があります。
居抜きオフィスとは何か?
前の入居企業が使用していた内装や設備、オフィス家具などを撤去せず、そのままの状態で次の入居企業に引き継がれる賃貸オフィスを指します。通常の賃貸契約では退去時に原状回復義務がありますが、居抜き形態では前テナントの原状回復義務が免除され、次のテナントがその状態を引き継ぐ形となります。
居抜き物件との違い(スケルトン、セットアップオフィス等)
スケルトン物件は内装や設備がすべて撤去された骨組みだけの状態で、ゼロから内装工事が必要になります。セットアップオフィスは貸主が新たに内装工事を施し、その費用を賃料に含めて貸し出す形態です。居抜きオフィスは前テナントの使用状態を引き継ぐため、中古の設備や内装を活用する点で両者とは異なります。
残置物・造作物として残される要素(内装、什器、設備)
オフィスに残される要素には、パーティションや間仕切りといった内装造作、デスクやチェア・書類棚などの什器、照明器具やエアコン・給湯設備などの設備機器が含まれます。カーペットやブラインド、配線設備なども残置物として扱われ、造作譲渡契約によって有償または無償で譲渡される場合があります。
契約形態・権利関係上での扱い
賃貸借契約とは別に、前テナントと新テナントの間で造作譲渡契約を結ぶケースが一般的です。造作物の所有権や原状回復義務の範囲、不具合が発生した際の責任所在などを明確にしておく必要があります。リース契約が残っている設備については、契約者の変更手続きや返却の判断が求められます。
居抜きオフィスが注目を浴びる背景・トレンド

近年、居抜きオフィスへの関心が高まっている背景には、複数の社会的・経済的要因が絡み合っています。企業の働き方改革やコスト意識の変化、さらには環境配慮への意識向上など、多角的な視点から居抜き物件の価値が見直されている状況があります。
コスト高騰と資材調達の難しさ
建設資材の価格上昇や人手不足による人件費の増加により、内装工事費は年々高騰しています。世界的なインフレの影響で、オフィスの新規内装にかかる費用負担は企業にとって大きな課題となっており、既存の内装を活用できる居抜き物件が経済的な選択肢として評価されています。
企業のオフィス規模縮小・移転頻度増加
コロナ禍を契機にテレワークが浸透し、オフィスの出社率が低下した結果、多くの企業がオフィス規模の見直しを進めています。ダウンサイジングや拠点の再配置により移転頻度が増加し、短期間での移転や一時的な利用を想定した柔軟なオフィス形態として、居抜き物件が選ばれやすくなっています。
オフィス空室率の上昇と物件供給構造
都心部を中心にオフィスの空室率が上昇しており、貸主側も空室期間を短縮するために居抜き形態での貸し出しを承認するケースが増えています。使用年数が短い物件や、ハイグレードな内装が残された物件も市場に出るようになり、居抜きオフィスの選択肢が広がっています。
持続可能性(廃棄削減・リユース志向)の潮流
既存の内装や設備を再利用する居抜きオフィスは、原状回復工事に伴う廃棄物の発生を抑え、環境負荷を低減します。SDGsの観点から資源の有効活用が求められる中、サステナビリティを重視する企業にとって、居抜き物件の活用は環境配慮の姿勢を示す手段にもなっています。
居抜きオフィスを利用するメリット
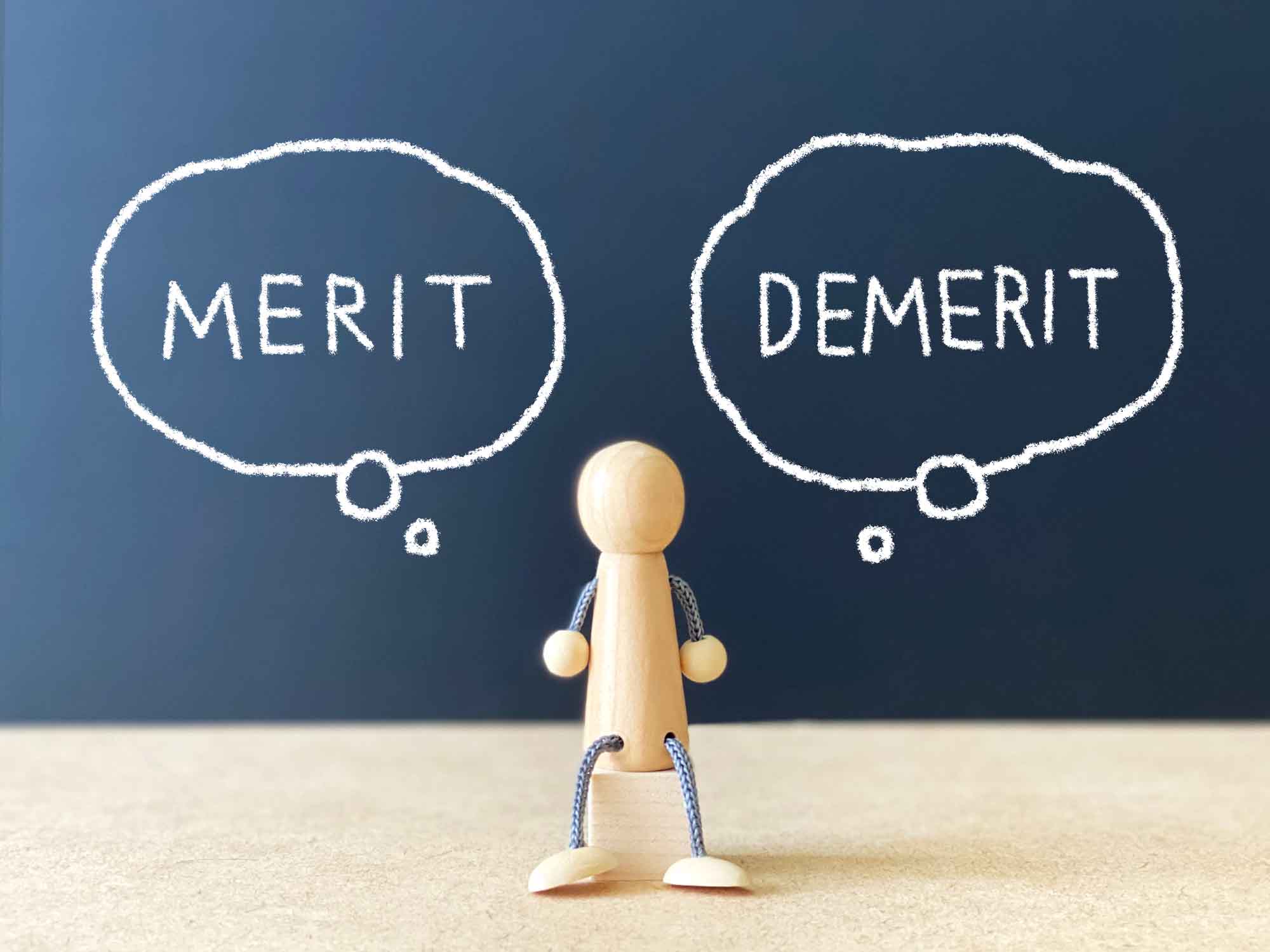
初期費用や移転期間の削減だけでなく、賃料面や退去時の負担軽減など、居抜きオフィスには複数のメリットが存在します。企業規模や業種を問わず、多くの企業が実際に享受している具体的な利点を把握すれば、自社にとっての導入価値を判断しやすくなります。
初期費用の削減(内装・什器導入コスト)
一般的なオフィス移転では坪単価20万円から40万円程度の内装工事費が発生しますが、居抜きオフィスでは既存の内装を活用できるため、大幅なコスト削減が可能になります。デスクやチェア、書類棚などの什器も揃っている場合、購入費用が不要になり、初期投資を最小限に抑えられます。
移転準備期間・工事期間の短縮
内装工事には通常1〜2か月程度の期間を要しますが、居抜きオフィスでは工事が不要または最小限で済むため、契約から入居までの期間を大幅に短縮できます。業務の中断期間を最小限にとどめられるため、事業継続性を重視する企業にとって大きな価値があります。
賃料・共益費の競争力があるケース
セットアップオフィスでは内装費用が賃料に上乗せされるため、相場より高額になる傾向があります。居抜きオフィスは前テナントの残置物を活用する形態のため、賃料は通常の賃貸オフィスと同程度に設定されるケースが多く、月々のランニングコストを抑えやすくなります。
退去時の原状回復負担軽減の可能性
居抜き形態で退去する場合、次のテナントに造作物を引き継ぐため、原状回復工事が免除される可能性があります。後継テナントが早期に決まれば、解約予告期間中の賃料支払いを削減できる場合もあり、退去時の経済的負担を軽減できる選択肢となります。
居抜きオフィス利用時のリスク・注意点
コスト面でのメリットが大きい一方で、居抜きオフィスには特有のリスクや注意すべき点が存在します。契約前に把握しておかなければ、想定外の費用負担や使い勝手の問題に直面する可能性があるため、慎重な確認と判断が求められます。
残置物の状態不良・修繕・交換コスト
前テナントが使用していた設備や什器は中古品であるため、経年劣化や故障のリスクがあります。エアコンや照明器具、給湯設備などに不具合が見つかった場合、修理や交換費用は入居企業が負担するケースが多く、初期費用削減のメリットが相殺される可能性もあります。
レイアウト制約・使い勝手のズレ
前テナントの業種や規模に合わせて設計されたレイアウトが、自社の業務スタイルや組織構造に適合しない場合があります。会議室の数や配置、オープンスペースと個室のバランスなど、既存のレイアウトを大幅に変更すると追加工事が必要になり、かえってコストが増大するリスクがあります。
契約条件・原状回復義務の引き継ぎ可能性
居抜きオフィスに入居する際、前テナントの原状回復義務を引き継ぐ形になる場合が多くあります。退去時には前テナントが施した造作も含めて原状回復を求められる可能性があり、想定以上の費用が発生するリスクがあります。契約書で原状回復の範囲を明確に確認する必要があります。
設備・配線・法令適合性チェックの重要性
前テナントの入居時から年数が経過している場合、消防法など法令の改正により、既存の設備が現行基準に適合していない可能性があります。法令違反が発覚した場合、入居企業の負担で改修工事が必要になる場合があるため、事前に専門家による確認が欠かせません。
居抜きオフィス物件の選定ポイント
居抜きオフィスのメリットを最大限に活かし、リスクを最小限に抑えるには、物件選定の段階での入念なチェックが不可欠です。内覧時に確認すべき項目や契約前に整理しておくべき条件を把握すれば、失敗のない物件選びが実現できます。
残置物・什器のリストアップと状態確認
入居前に造作譲渡契約書や譲渡品リストを確認し、どの設備や什器が残されるのかを明確にする必要があります。メーカー名や型番、購入時期、傷や汚れの状態、リース品の有無などを記載した詳細なリストがあれば、トラブル防止につながります。写真付きの記録があるとより安心です。
レイアウト変更可能性と可変性の有無
既存のレイアウトが自社に適合しない場合、どの程度の変更が許容されるのかを貸主や管理会社に確認する必要があります。パーティションの移動や間仕切りの撤去が可能か、変更に伴う費用負担は誰が担うのかを事前に明確にしておけば、入居後の使い勝手の問題を回避できます。
設備・空調・電源・通信インフラの状況
エアコンの設置年数や稼働状態、電源容量、通信回線の種類と速度など、業務に直結する設備の状況を詳細に確認する必要があります。特にIT企業やクリエイティブ業種では、高速インターネット回線やサーバー用の電源確保が重要になるため、自社の業務要件と照らし合わせたチェックが欠かせません。
契約書類・貸主条件・責任範囲の確認
賃貸借契約書だけでなく、造作譲渡契約書、原状回復基準書、現状確認書など、複数の書類を細かく確認する必要があります。契約不適合責任の所在、リース契約の引き継ぎ条件、退去時の原状回復範囲など、後々トラブルになりやすい項目は専門家のアドバイスを受けながら慎重に検討すべきです。
活用事例と導入プロセス、運用のヒント
実際に居抜きオフィスを導入した企業の事例や、契約から入居までの具体的な流れを知れば、自社での導入イメージがより明確になります。運用後のメンテナンスや工夫次第で、居抜きオフィスの価値をさらに高められる可能性もあります。
国内企業での居抜きオフィス導入事例
スタートアップ企業では、資金調達後の迅速な拠点拡大のために居抜きオフィスを活用し、初期費用を研究開発や採用に充てる戦略が見られます。中堅企業では、プロジェクト単位での短期利用や、テレワーク併用に伴うオフィス縮小の際に居抜き物件を選択し、移転コストを大幅に削減しています。
導入ステップ(選定 → 契約 → 手直し → 入居)
物件選定では、立地や広さだけでなく残置物の状態や契約条件を総合的に判断する必要があります。契約時には賃貸借契約と造作譲渡契約を同時に締結し、原状回復の範囲や費用負担を明文化します。入居前には必要最小限の手直しを行い、ネットワーク環境やセキュリティ対策を整えてから業務を開始します。
運用後のメンテナンス・見直しポイント
居抜きで引き継いだ設備は中古品であるため、定期的な点検とメンテナンスが重要になります。エアコンのフィルター清掃や照明器具の交換など、小まめな手入れが故障リスクを低減します。業務内容や組織体制の変化に応じて、レイアウトの微調整や什器の追加購入を検討すれば、使い勝手を向上させられます。
居抜きオフィスを有効に使うための工夫
既存の内装に自社らしさを加えるには、クロスの張り替えや植物・アートの配置、照明の変更など、大がかりな工事を伴わない方法が効果的です。休憩スペースにソファやカウンター席を追加する、カラーリングを変更するといった小規模な改修でも、従業員の満足度向上や企業ブランディングにつなげられます。
<おすすめの配線用開口オプション付きテーブルはこちら>
まとめ
居抜きオフィスは、初期費用と移転期間を大幅に削減できる実用的な選択肢であり、環境配慮の観点からも評価が高まっています。契約条件や設備状態を丁寧に確認し、自社の業務要件に合った物件を選定すれば、コストとスピード、快適さを両立したオフィス環境を実現できます。



